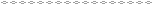ふと夜中に目が覚めた留三郎は、それからなかなか寝付けないので水でも飲もうと庭へ出た。
忍ぶには格好の、朔の夜であった。近頃段々と夏に向かいつつあって日中はじっとりと汗ばむような陽気であるが、この時刻になると過ぎ去ったはずの季節がひそやかに舞い戻らんと機をうかがっているかのように、気温がぐっと下がる。雑草の伸びつつある地面に立てば、夜着からむき出しの足元を撫ぜながら、ひんやりとした風がまとわりついた。
井戸は庭を横切った隅の方にある。
厠が近いので、鼻の奥底をきゅっとつまむような特有の生のにおいが流れてくる。まだ本格的に暑くは無く、言ってみれば生活の中常にある臭気であることから慣れもあって不快というほどではない。
踏み出すごとにさやさやと草ずれがする。音と言えばそれだけだ。
星明かりだけを頼りに井戸まで行き、釣瓶を使って水を汲み、手に受けて飲む。井戸の底に釣瓶が当たって、かーんという好い音が深夜のしじまに響きすぎるくらい響いた。飲みこぼした水が一筋、喉を伝って襟元を濡らす。数分もすれば乾くであろうその湿り気が、今は妙に冷たく感ぜられた。
と、耳が気配を捉えた。
動物にしては大きい。
忍たまのならいで瞬間に全身を緊張させた留三郎にお構いなしに、その気配はずんずんと近づいてくる。だいぶ近いであろうに、はっきりとした足音は聞こえないことから、少なくとも下級生(もしくは小松田さん)では無いらしかった。
そして、闇夜に人の形が凝る。
猫を思わせる細身に、まっすぐな長い髪。知らず、あ。と留三郎の声が漏れ出た。
「食満か。…寒いな、今夜は」
青白い仙蔵の面がぼんやりと後はただ暗いばかりの影に張り付いている。表情を見るには暗いが、いつもの紅い花のような笑みが灯っているのだろうと思った。
「ああ」
ほんのわずかな言葉を交わせば、後はただ喋る用も無いので留三郎は自室へと足を向け、仙蔵に井戸を明け渡す。
彼ら二人がすれ違うその刹那、下ろしてある仙蔵の髪の束がそよかに煽られて留三郎の鼻をかすめた。
それはぷうんと、獣の臭いがした。
「え、それ本当?」
「ああ、確かにあれは何か動物の臭いだ。こう、生物小屋の近くで嗅ぐような…いや、違うな、もっとあれはこう、野生っぽい感じだった」
「でもさでもさ、仙蔵だってそれこそ何か生物小屋に用があったのかもしれないし!」
「夜中に?」
「う」
「立花だぞ」
「うー」
獣遁の術は必須科目であるし、勿論何事にも手を抜かないかの友人はその辺りもきっちり履修しているのだが、どちらかというと相性が悪いようだった。
「子どもと動物は話が通じない」とこぼしていたのを見聞きされている。
それであるから、用が無ければ生物小屋になど寄りつかないだろう。
「…てことは、もう留さんは信じているんだね?」
「え、いや信じてないぞ」
まだ、という条件を危うく呑み込んで、留三郎は首を振る。と、ずずいっと伊作が顔を寄せてきた。
「じゃあその夜の出来事はどう説明するわけ?」
「ぬっ…」
言葉に詰まったところで伊作が満足げな息をフフンと漏らすので、「で、お前は結局信じてるのかよ」と逆襲してやった。
伊作はうーん、とか、あーとか散々言いあぐみ、
「…いやだってほら、不可能を除いて行った先にあるのが、いかにあり得なさそうに見えても真実だって、ホームズも言ってたし」
「誰だよ」
そうして何となく二人黙って、雨漏りのしそうな天井を見つめていれば、どこからか獣の遠吠えが聞こえてきた。この雨夜をしのぐ場所が見つからぬのか、それは腸を細くよじり合わせるように長く長く、悲しげな響きであった。
留三郎は人の熱で温い布団に一層深くもぐりながら、しとどに濡れた狼の白銀の毛皮と、吠えるたびに高く掲げられる美しい鼻先の流線を思った。
「仙蔵がさ、もしもだよ。信じてないけどたとえばの話、本当に狐だとしたら」
遠吠えの小さく遠くなる尾にかぶせるように、伊作がぽつりと言う。
「正体がばれたらやっぱり学園を出て行ってしまうと思う?」
「…そうなるだろうな」
三年も終わりに近づくころから、休みが終わっても学校に戻ってこない級友がちらほらいるようになった。張り合っているとはいえどこか圧倒的な違いを感じさせる四年生の、人数は三年よりずっと少ないのである。
「これ以上僕らの学年の人数が減るの、嫌だなぁ」
「ああ」
「この話、僕は留以外にはしない。うん、誰にも言わない。だから留さん?」
そうして、留三郎の肩のあたりの布が物言いたげに引っ張られる。
「…じゃ、俺は忘れたことにしておくか」
うん、と返ってきた返事は柔らかく、自分をこの寒々しい夜から守る綿入れの布団の手触りに似ていた。話したことなど碌にないい組の立花仙蔵に義理も借りも無いが、こうして級友が夜目も聞かぬ闇の中で笑っていられるなら、口を噤んでおいてやってもいいか、と思うのである。外は雨、部屋には隙間風だが、並んで敷かれた寝床二枚分だけはじんわりと他の何物でもない自分たちの熱で温もっている。
「寝ようか留さん」
「おう」
そうして眼を閉じれば、瞼の奥にちらちらとして白いものが踊る。それはあの夜中に見た級友の薄白い面であり、独り在っておめく獣の毛並みであり、雲の向こうにあるはずの月の丸さなのだ。とはいえ、本当にこの押しかかるような質量を持った鉛色の雲の奥にいつもの清かな月があるのかどうか、問われて是と答える確証はないのだったけれど。
留三郎はそのうち、いつ果てるとも知れぬ薄野を彷徨っていた。薄明るいだけで色の抜けきったぼんやりした空が広がり、そこかしこに鬼火が灯っては消える。足のつかれようからして随分長く歩いているのだが、行けども行けども景色は変わらない。
彼以外に人の気配は絶えてない。
不安に駆られ振り返れば、仙蔵に似て澄ました顔をした白い狐が、けっけっけと高く啼きながら横を走り抜ける夢であった。
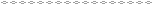
六年生は悪ノリだったと思われます。室町時代は妖怪を信じられる時代!
三年までは低学年。
家の事情でやめていく子もいるけど、大体まだ揃ってる。
→四年になって授業激化。体力的かつ精神的にもハードになるので、脱落者続出してクラス合同授業が多くなる。
→い組とは組の面々が仲良くなるのは四年になってからかなという設定。
おまけへ mainへ