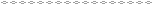お前なぁ、と滝夜叉丸は教科書を放り出すと、匍匐前進で部屋の向かい側まで進もうとしていた喜八郎の先をたった二歩で追い越し、さっきまでカーリングの駒と化していた気の毒な本を拾い上げた。心なしか、何度もこすられた表紙の紙が薄くなったような気がする。
「それ私の本」
「本は読むものであって、滑らせるものじゃない」
どこぞの図書委員のような物言いである。とはいえ、この本だって図書室からの借り物であるので、確かに今までの扱いが知れたら同じお小言をいただくことだろう。
「どこまで読んだ?」
「三」
「三章か」
と、まだ指を通してもいないページを開こうとするので、喜八郎は親切に教えてやった。
「そうじゃなくて三ページめ」
がくん、と滝夜叉丸の顎が開いて、眉がハの字に顰められる。あ、呆れてるなと喜八郎にも分かって、そこが滝のいいところなんだよねと心中で感想を述べた。
「三ページって、全然読んでないのと同じじゃないか」
「つまんない」
「またそんなこと言って…。明日までじゃなかったか、この課題」
一応確認形ではあるが、もちろん滝夜叉丸は正確に期日を知っている。とはいえ三日前には終わらせているのが常なので、彼のその知識はもっぱら喜八郎用備忘録と化している。しかも、期限が迫ると教えてくれる便利機能付き。ついでに部屋にかけてある暦にも自動記入してくれる。喜八郎は見ないが。
「そうだっけ」
「そうだ。まったく、喜八郎は読みはじめれば早いのに。しかも一回読めば覚えるんだから、早く読んでしまえ」
「やる気がない」
今度は床板の木の節についた年輪を数え始めながら彼は宣言した。すぐに数え終わりそうだったが、細かいので途中で計算を忘れてしまってなかなか終わらない。よく見れば、外側に行くにしたがって円は二本の曲線へと別れ、徐々にまっすぐになり、幹を走っていたであろう大きな流れと一体になっていく。あ、これどこかで見たなと、渓流に飛び出た岩やそれを迂回していく水流を思い返す喜八郎の頭の中には、いつか遠足でいった深山の渓流が広がっている。この季節、涼しくて大変よろしい。どこを見ているかわからないと普段言われる喜八郎の目は今ばかりは皿のように見開かれ、数尺先の節を注視している。
はぁ、としっかり聞こえる溜息をついて、滝夜叉丸は未だごろりと伸びたままの喜八郎の肩を本で軽く小突いて、注意を板間から逸らした。河鹿鳴く清流はその一突きで夏の生ぬるい空気に溶けて行って、喜八郎はやっぱり渓流ではなく板目を見ていた。残念だが、板は程よく冷たくて、これはこれで気持ちがいい。
「ほら、私も読む本があるから、一緒に読もう」
「滝の読む本って忍たまの友?」
「別のだ。まだ借りてきた本を消化しきれてない」
部屋の滝夜叉丸側の書机の横にある、風呂敷包みの中身を指して言う。この風呂敷包みがぺしゃんこになっているところなど、喜八郎は未だかつてお目にかかったことがない。だが、消化とこの友人が言うからには、この一見常に同じ高さの中身は目まぐるしく入れ替わっているのだろう。
だが、喜八郎だって本は読む。部屋に二つ備えられた書机のうち、喜八郎側の物の上には、しおりが挟んであったり、伏せてあったりする本がいつも三〜四冊はおいてある、というより積み重ねてある。自分に興味が持てることならば、そして気分が向いたならば、彼はそれこそむさぼるような勢いで誰かが下手な手で模写したらしい崩し字を易々と読んでいくのだ。だが、今回の課題の図書は南蛮の体術の歴史についてで、実践ならいざ知らず遠い異国でのある流派の拡播の過程を知って何になるのかいまいち納得しがたい。
「だって滝は興味がある本を読むんでしょ」
「読まなければならない本は終わったから」
さっさと例の風呂敷包みの中身を取り出して、こちらもしおりの挟まった何かの本を取り出した滝夜叉丸は、当然喜八郎もその疇に従うものと疑いもせずこちらを見ている。
「それもそうか」
口に出して言えば、少しは納得できるような気がした喜八郎は、渋々と滝夜叉丸の差し出す課題図書を受け取り、三ページめを開いた。段々外も暗くなってきたので、油皿に油を足して、火をつける。塞いでも塞いでもどこからか入ってくる隙間風に揺れる火で、黄ばんだ紙に残った流麗な墨跡もゆらゆらと動きだした。
「先に読み終わらないでよ」
「いつもどうせ喜八郎が先に終わるんじゃないか」
もう本に没頭しているのか、一度書見台に反射してから帰ってくる滝夜叉丸の声はくぐもっている。背筋に沿ってぴんと肩から落ちる紫色の制服と、微動だにしない髷の先が見える様な気がした。
「滝と一緒に読んでればね」
「なんだそれは」
律義に同室者は返してくれたが、喜八郎のスイッチはもう読むモードへと切り替わっていた。あれほど進まなかった読解が、一行丸のまま意味を持つ塊となって喜八郎の脳に流れ込んでゆく。その久々の感覚を楽しみながら、そのうち自分が集中しているということすらも、押し寄せる文字の波の中に洗われて溶解していくのだ。だけれども、そうした読むのに邪魔な感傷が墨色の海に解けていく一瞬、少しだけ流れが温んだ。遠い霧の中に見た灯台の黄色い火のように。
なんだろう。
文字を追うのをやめて、一瞬陸の方に舞い戻る。だが、その時にはもうあの灯りは笊の様な喜八郎の自意識からすっかり抜け落ちてしまっていた。気になる、気になるけれども、結局こういうのは考えたってこの感情が何なのか自分に見定められたためしがない。
やっぱり早く読んで、終わらせてしまおう。喜八郎は今度こそ思い切りよく、書面に意識を没頭させた。頭の中をあの板の間に写された奔流のような勢いで文字が流れていく。再び彼と文字以外のすべての事象は意識から遠のいていくが、どこかで最後の雑念が小さく囁いている。
早く読んで、これが終わったら、また穴を掘ろう。
分からないことは、穴を掘り足りないせいなのだから。
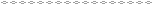
なんとなく、滝に感謝してるんだけど意識に上らない綾部。やればできるのに、やらない人綾部。速読できるので、その気になれば物凄く早いと良い。だけど結局変人綾部。
mainへ