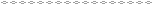じっと先輩の後ろ姿を眺める。巻物に集中しているのか、若干猫背気味になっている様子からして、しばらく振り返らなそうだ、と見当をつける。
もし見られたら、いかに優しい先輩とはいえこの部屋から追い出されてしまうだろうけれど。
そうっと、音がしないように細心の注意を払いながら、そのかんざしを二本の指でつまみあげる。ひんやりと冷たい。
髪に挿しやすく尖らせてある先端をニ、三秒観察すれば、若干周りと比べて変色を起こしているような気がした。それが毒によるものなのだろうか。
そうして、ほんの一瞬。
私の舌は冷たい鉄の上をなぞった。
見つからぬうちに、とかんざしを素早く、だが気をつけて床に戻す。
目を閉じて、舌に残るぴりりとした苦みを味わった。茶や内臓の苦みとは違う、いつまでも纏わりつく妙に甘いような苦みだ。
ちょっと舐め取ったくらいではいかに強い毒であろうとどうなるわけではあるまいに、そうして苦みのことを考えていると心の臓がきりりと縮こまって痛むような気さえしてくる。
私は毒物の事には明るくないが、これが直接突き刺さればきっともう助かるまいと思う。
この鉄の先端が突き破るのは、恐らく彼の人を捕えることになったどこぞの忍びの心臓ではあるまい。
かんざしなどという小さな道具が使えるのは正しく一度きりなのだから。
一度きりで確実に、ある苦境から逃れるためにこの凶器が使われるのは、ああ、考えたくも無い!
考えたくは無いのに、私の忌々しい想像力はまざまざと日に焼けない白い肌、そこへ黒々と突き刺さった黒鈍色の鉄を思い描く。それを握りしめる、色を失って青白くさえある指のさきの千鳥を想うと、私の舌はまた勝手に喋り出していた。
「ということは」
「なんだ、またか」
先輩はこちらを向いてくれない。
私の頭の中には、きらびやかな女装束に身を包んだ先輩がゆっくりと倒れ伏す映像が蜃気楼のようにちらついていて、聞こえている声はまるで私らしくなく上ずる。
「そのかんざしを、明日先輩は着けていくんですか」
こんなに切羽詰まった声は、私の声ではない。これではまるで、親に置いてかれようとする、無力で無能な幼子ではないか。
「あのな、綾部、」
細く息を吐き出して、先輩は膝をずらして体ごと振り返った。先輩が見た私の表情など、先輩と天の神以外は恐らく一生知り得ないだろう。
「大丈夫、心配するな。これを使うなんてことは明日の内容なら万に一つもあるまい。これはただ…保険みたいなものだ」
「…」
「な、だから、そんな顔をしてくれるな。ちゃんと、帰ってくるから」
先輩を困らせるのは本意ではなかったので、ただ私は頷いた。たとえ頭の中でめくるめく悲劇が上映されていたって、先輩の忍務遂行能力に対しては一点の疑いも無い。別に、先輩が帰ってこないかもしれないなんてことを心配しているわけではない。
ただ。
ただ、視界を埋め尽くすように広げられた、美しいばかりの衣々の中に、そのかんざしがあると言う事実が私の心をひどく揺さぶる。
完璧に装って道を行く、むし垂れ衣姿に止まる千鳥の嘴が、私の一番ひとらしい部分をしきりにつつく。
だけどもそれを説明する事は口下手な私には到底できそうにも無いことであったので、物分かりのよいふりをして無言でうなずくほかは無い。
納得したと思ったのか、先輩は小さく頷き返してまた書物に戻る。だんだんと暗くなる部屋の中では、先輩のいる壁際は特に沈んでいて、深緑色の装束の色など土壁の陰さに同化してしまっているようだ。
私は腹ばいの姿勢から起き上がり、膝を曲げ、その膝を抱え込むように座りなおして障子の方を眺めた。
斜陽に染まった障子紙は、よく熟れた柿の暖かな朱色だ。壁一面に広がるただ一色の鮮やかな朱を、黒い桟が直角に仕切っている様子はとても美しいものであった。そして、それを見つめる私の両目にもその美しい光景が一杯にうつりこんでいるのだろうけれど、奥はぐろぐろと濁って渦巻いている。
外の強烈な熱を持った明るさと反比例して、彩度を失っていく薄暗い部屋の中、小指の先ほどのざくろ石がてらりと光る。かんざしなど薄っぺらいものであるのに、限界まで低くなった日のおかげで、その影はぐんと伸びて板間にひと際黒く染みを作っている。
さて、こうして中央に縮こまる私の影は、先輩まで届いているのだろうか。
口に含んだ苦さはまだ舌に残っている。
「ねえ、先輩、先輩」
彼の人の名を呼ぶ。この祈りは、身勝手である。
「そんなことは止してくださいね。悲しみます」
しおえせんぱいが、と聞こえないように付け足した声音の、我ながらなんと感情のこもっていないものか。
しないよ、と返ってきた声は、とてもとても優しいものであったのだけれど。
もう日が落ちる。そうすれば夕食の時間になり、私と先輩は連れ立って食堂に行くだろう。そこで私は同級生と、先輩には先輩の同級生と座ることになって、私たちは何も特別な儀式も無く日常の延長のままに別れるのだろう。そのまま私は自分の長屋に戻り、もう互いに顔を見ることも無いまま、次の朝早く先輩は実習に出かける。
別段、何が特別なわけでもない。
先輩の居ない委員会は今までも何度もあったし、先輩にとっては明日もいつものような
「お使い」の一つにすぎないのだろう。だけれども、私の側の、先輩が実習に出かけると言うことについての認識は今日を境に決定的に変わってしまった。
私は先輩についていけないが、その人の結いあがった髪の毛には常にあのかんざしがある。潮江先輩のかんざしが。
秋がひとこいしいとは、こういうことを言うのかと知った。
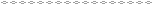
6い祭に投稿させていただきました。
mainへ