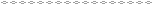刀を握ったまま膝をついた文次郎が振り返ると、山賊たちの間からぬっと現れた鷲鼻の手に、煙をあげる火縄銃があった。黄色い歯で乏しい蝋燭の光を跳ね返し、にぃっと笑う。
「貴様ら最初から組んでいたな。接吻しながら縄を切ったのを見過ごすと思うてか」
文次郎は痛みをこらえて背後の仙蔵と木乃伊を振り仰いだ。仙蔵の紅い口元が一瞬開きかけてまた閉じる。蝋燭の揺らめきでちらりと紅い輝きが走り白い歯が覗く光景は充分に艶めかしくあったが、肩の突きさすような痛みのおかげで、先程から頭蓋を内側から突き破りそうだった衝動が引いていくのを感じる。
「ふん…これじゃあどんなに舞ったって、天の岩戸が開くわけもねェな」
洞窟に、鷲鼻の男の哄笑が響く。
「驚いたか。それが我等のおかしらよ。基成さまに亡くなられては困るのでなァ…。
だが知られては生かして出すわけにはゆかん。そこの女共々、仲良く土塊にしてやろう」
火縄の先に再び火が灯される。
指が引金にかかったとき、文次郎の右手が素早く動いた。空を走る手裏剣は火縄銃を構える手に突き刺さり、はずみで地面に落ちた火縄銃は腹をえぐるような轟音とともに暴発した。
煙が狭い岩屋に満ち、暗かった視界をさらに悪くする。
「文次郎っ!」
ふいに手が引かれた。頬に絹のような髪があたる感触がある。煙のむこうから仙蔵の声がした。
「見ろ、あの隅に煙が吸われていく。あそこに火薬を仕掛けて脱出するぞ」
「分かった」
文次郎は祭壇から無造作に蝋燭を掴み、仙蔵に手渡す。
「俺が食い止める。とっとと仕掛けて来い」
きらりと鋼が輝き、続いて山賊の短刀が振り下ろされる。それを右手一本の刀で受けて、文次郎は回し蹴りを喰らわせた。続いて横に刃を払えば確かに手ごたえがあった。蝋燭の光は煙に遮られ届かないが、人体の熱や息遣いから敵の動きは手に取るようにわかる。今や岩屋は、火薬の臭いと金属音と金切り声、得体の知れぬうめき声で溢れていた。ず、と足元が滑り、出血していることを思い出す。この暗さでは出血の量もわからない。こめかみがずきんずきんと脈打つのを感じるが、とにかく今はそれほどの傷でないことを祈るしかなかった。
その時再び爆音が轟き、急に光が差した。さすがに身体の向きを考える余裕の無かった文次郎はそのまぶしさを正面に浴び、目を細める。その瞬間、左肩に何かがぶつかり、思わず呻いて刀を取り落とした。
「阿呆!」
緋色の影が横を走り、背後で野太いうめき声が聞こえる。
「文次郎、とっととその穴から出ろっ!」
同時に太ももを蹴りあげられ、押されるように文次郎は転がり出た。文字通りでんぐり返しをするような格好で、岩を崩した穴から、苔の生えた木の根だらけの地面に投げ出される。突然の明るさと、さらに痛みを増した左肩のせいで靄がかかったように目がかすんでいる。
肩で息をしながら起き上り目をこすって振り向いた瞬間、本日何度目かの爆音とともに、地を震わせながら岩屋はがらがらと崩れ落ちた。
適量の火薬が爆発し狙い通りの穴が空くと、差し込んだ光の中、右手で肩を抑える文次郎が浮かび上がった。咄嗟に身を起こした仙蔵は、彼の後ろで鉈を振り上げていた山賊に当て身をくらわす。ついでに乱暴に文次郎を蹴り飛ばし、宝禄火矢を求めて懐に手を入れたとき、鉄の棒が唸りをあげて飛んできた。避けようとして、先程の破裂で吹き飛んだ岩に裾が引っ掛かっているのに気付かなかった。バランスを取り戻そうと空を切った腕が万力のような手に捕えられる。そのまま抱きすくめられ丸太のような腕で抑えつけられた。横目でそれがあの鷲鼻だと分かるほどすっかり視界がきくようになった岩屋で、立っているのは自分と自分を捕えた男と、あとは数人だけだった。
耳のすぐ横で鷲鼻の男の荒い呼吸を感じ、首筋を舌が這う感覚に、仙蔵の全身が鳥肌立つ。
「たっぷり可愛がってから殺してやる。男のほうもすぐ始末してやろうぞ」
太ももに這わされた手が小袖の裾をまくり上げ始める。仙蔵の耳にねっとりと熱い息を吹きかけながら身体をまさぐりだした手が止まった。
「な…」
「ふん、今さら気づいたか?」
冷笑する仙蔵の手には二つの宝禄火矢が握られていた。
文次郎は痛みも忘れて立ちあがった。
どう考えても岩屋の爆発は仙蔵の仕業だ。それならば仙蔵はどこに居るのか。
濛々たる砂埃に邪魔され、崩れた岩屋の全貌すら定かではない。あれほど五月蠅かった蝉の声がぱたりとやみ、急にぽっかりひらけた空からは斜陽が差し込んでいる。ざわざわと葉ずれの音がいやに耳をつく。
「何を腑抜けている」
背後から聞こえた声に振り向けば、樅の木に身体を預け立花仙蔵が立っていた。
よく見れば手の込んだ刺繍の入っていた小袖はあちこちやぶけ、白い襦袢が埃と泥に汚れている。その顔もかしこに煤がついてはいるが、艶やかな黒髪はそのままで怪我もないようだった。
「せんぞ、」
「私がみすみすと巻き込まれるとでも思ったか」
「……せんぞう」
「どうした、ひとの名を繰り返しおって」
「…無事でよかった」
蝉が再び鳴き始めた。
肩の傷は幸い弾はかすっただけのようであったが、血が左半身を黒く染めている。だが今ははさほど出血はない。脚絆を裂いて止血しておけば、あとは動かさなければ学園までもつだろう。
処置を終え、日暮までに着ければよいがと山道を二人して下りだした時であった。
「あの木乃伊はなんだったんだろうな…」
「知らぬ。大方、基成とやらの後継者が後ろ盾に居て、死を隠しておきたかったのだろう。だが一人残らず岩に埋めたからな、あの木乃伊も今頃は土に還っていようよ」
「…伊作に持ち帰ってやったら喜んだかな」
「あんなものを背負った奴と同行なんて真っ平ご免だからな」
鼻で嗤った仙蔵だったが、一つ咳払いをして、
「ところで文次郎さま、」
「なんだ気色悪い。今さら女の声色なんざ遣いやがって」
「…わたくしのことは御心配に及びませぬ」
「なん…」
「なぜならば」
私を守っていたのはお前だろう、文次郎。
いつもの声に戻った仙蔵がそう言って、花のような笑みを見せた。
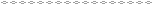
6い祭に投稿させて頂きました。
mainへ